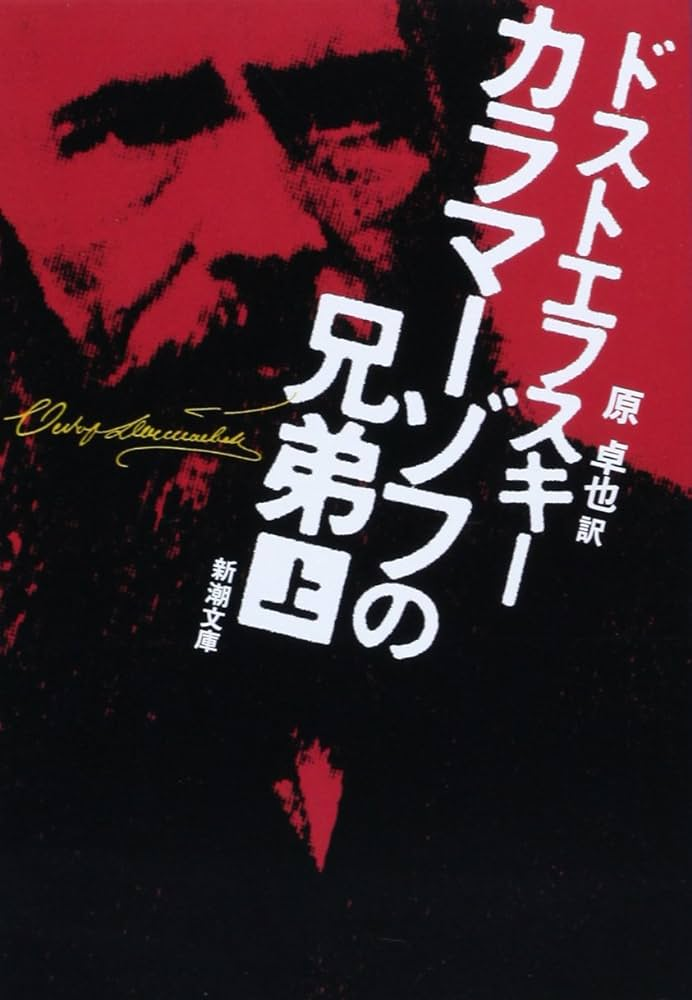
カラマーゾフの兄弟を再読しているのだが、父フョードルのこういうセリフが出てくる。
「わたしゃいつも、どこかへ行くと、自分がだれよりも卑劣なんだ、みなに道化者と思われているんだ、という気がしてならないのです。それならいっそ、本当に道化を演じてやろう、なぜってあんたらは一人残らず、このわたしよりも卑劣で愚かなんだから、と思うんでさ」
父親のヒョードルは女にだらしなく、守銭奴で、所かまわずにわめき散らす、どうしようもない人間として描かれている。ドストエフスキー流の表現を借りるならば、「カラマーゾフ的欲望の激流」を体現している男でもある。「たとえ全世界が火事で燃えようと、俺さえ楽しけりゃいい」という原理で生きてきた男なのである。しかし、誰よりも不幸であり、誰よりも憤りをその胸の内に積もらせ続けた人間でもあった。
この本を最初に読んだのは確か大学生の頃だったが、その時は「こじらせまくった自尊心の末路」くらいにしか思ってなかった。しかし、今読むとまた違った印象を受けた。
このセリフからもわかるようにフョードルは自分を「卑劣」で「愚か」と考えている。自分の言動や行為を理解しているし、他人が自分をそう見ているのも知っている。でもそれは変えようのない自分の本質なのだ。どうしようもないことなのだ。だからこそもっと「卑劣」で「愚か」な行為や言動をとることで、そんな自分を必死に守っている。それと同時に彼を嘲り笑う他人に対して、ひとつの真実を突き付けるのである。
「俺は自分の愚かさを嫌というほど知っているぞ、でもお前らは自分というものを、自分の愚かさを何ひとつ知らないだろう。いや、うすうすわかっていても目を背けているのさ。俺はお前らの本当の姿なんだよ、さあ、目を開けてこの俺を、滑稽な道化者をよく見ろ!」
そんなフョードルの叫びがこのセリフの奥には隠されている。彼は自分をどうしようもなく恥じている。道化の裏には、なんともしがたい羞恥心がある。恥知らずだから醜態をさらすのではない。恥じているからこそ、より愚かなふるまいをして、彼を嘲笑する人間を逆に嘲笑しているのだ。他人をあざ笑うことで、自分の愚かさから目を背け続ける人間たちに真実を突きつけるのである。なんとも悲しいふるまいのように感じるが、これもまた人間のひとつの姿なのだろう。
「恥の多い生涯を送って来ました」と「人間失格」で太宰は書いているが、恥を知らない人間はいともたやすく他人を嘲笑する。そうすることで、自分自身を「まともな人間」であると無意識のうちに刷り込ませるのだ。そういう人間にとって羞恥心とは単に外に、世間に対して向かっていくものであり、内に、自分自身に向くものではない。「人間失格」の大庭葉蔵も、フョードルもそれは自己へと深く沈んでいく。両者とも正反対のようでいて、根本的に似ているように感じる。表現方法が違うだけなのだ。そして、どちらも読むものにひとつの問いを投げつける。
御覧の通り、わたしはどうしようもない人間です。
でも、あなた自身はどうなのでしょう? と。
フョードルを見てバカにすることは、いともたやすい。しかし、その嘲笑はその瞬間、自分自身にも向けられるべきものである。そういう人間は自分の中に恥を見出す。恥とはゾッとする感情でもある。自分の中にゾッとするようなものが潜んでいることに、その瞬間、気がつくのだ。一方で嘲笑し続ける人間もいる。それもまた人間の姿なのだろう、と思う。